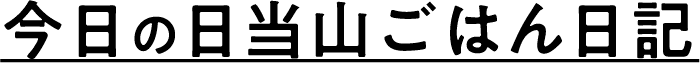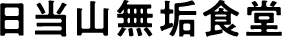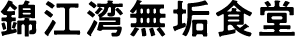蔵の歴史が詰まったハイブリッド麹。
手づくりのその先へ。
老舗の焼酎蔵で醸される昔ながらの製法
少し肌寒くなってきた季節、霧島市国分にある中村酒造場を訪れた。住宅と田んぼが多いエリアを少し迷いながらも歩いていると、突如目の前に現れた赤いレンガ造りで趣のある建物。ここが中村酒造場だった。
1888年(明治21年)創業、決して大きい蔵ではないが手づくりの焼酎にこだわり、創業時から使う蒸留設備も大切に受け継いで使っている。麹室は鹿児島県内で3つの蔵にしか残っていないという石造り、一次発酵に使用する和甕も今は造られていない貴重なものである。焼酎蔵の仕込みの時期の作業量はとてつもなく多い。そんな仕込みで忙しい中、快く取材を受け入れてくれた。
出迎えてくれたのは中村酒造場六代目杜氏の中村慎弥さん、ついさっきまで慌ただしく作業していたであろう中村さんは半袖のTシャツ姿で、寒くないですか?の問いに「今めちゃめちゃ暑いです」と爽やかな笑顔で応えてくれた。
周りに住宅が多いことに驚いたと話すと「昔は蔵の周りは殆ど田んぼだったんですけどね。気付けば家がたくさん建っていました」と、この地でずっと地域を見守ってきた焼酎蔵に134年という時間の長さを感じた。

家族が幸せに笑っている
風景を描きながら
中村さんに、なぜ家業を継ぐ道に進もうと思ったのかを聞いてみると、なんともドラマチックな物語が待っていた。
サッカー少年だった中村さん。それを聞き「そうか、この爽やかさ、どこか脳裏に残っていると思ったら、学生時代に感じたサッカー部のものだったか」と、自分で勝手に納得してしまった。そんな中村さんは、高校ではパソコンや工業系のことが好きだったので、物理を勉強できる道へ進もうかと考えていた。一方、家では両親たちが昔ながらの製法を守り焼酎造りをしていた。隣で見てきていたが、特に手伝うこともなく、親とも代継ぎの話はしていなかったので焼酎蔵とは一定の距離がある状態だった。
中村酒造場の運命が変わったのは、SMAPが歌う『世界に一つだけの花』が大ヒットした2003年、日本に本格焼酎ブームが巻き起こり、オンリーワンの焼酎を求めた消費者がこぞってマイナーな焼酎を探し求めるようになったところから。本格焼酎は糖質ゼロ、プリン体ゼロなどの特徴と、日本人の健康志向も合わさり、その人気は爆発的だった。焼酎の出荷量は日本酒の出荷量を約50年ぶりに上回り、翌年には売上高もピークを迎え、好きなお酒ナンバーワンにも選ばれるようになってきた。
そんな本格焼酎ブームで手づくりを貫いてきた中村酒造場の知名度も広がり、瓶に詰めてラベルを貼ったそばから出荷され、蔵に在庫が無くなるほどの状況がやってくる。「大きくはない蔵だが100年以上も古くからの伝統的な製法を守り、実直に焼酎を造り続けてきた長年の苦労が、こんなにも劇的に報われる時が来るのか」と中村さんの心に大きな衝撃が走った。家族、従業員含め蔵に関わる全員、特に大変な時代を乗り越えてきた祖父母が、心底嬉しそうにしている様子を見たとき「この蔵を途絶えさせてはいけない、この手づくりを守っていこう」そう決めた。
それからは進路の方向をぐるっと変更し、東京農業大学醸造科学科へ進学し酒造りについて学んだ。大学卒業後、山形県の日本酒蔵で醸造酒を造る現場を肌で体験し、その後は大阪で酒の流通に携わり、売り手も酒蔵の想いを共有し、さらに買い手にその想いが伝わらなければ、酒蔵が良い酒を造っていても届かないと学ぶ。
2012年、鹿児島に戻ってきて中村酒造場で働き出した中村さんは、そこから4年間、阿多杜氏の最後のひとりである上堂園幸蔵氏の下で焼酎造りの技術はもちろんのこと、焼酎造りに対する姿勢など精神的な部分もたくさん学び、ついに中村酒造場の杜氏となるのである。

米、芋、水、全てが霧島
中村酒造場で芋焼酎を仕込む過程では、地元で収穫された米を蒸し、その米に種麹を撒き、麹室で大事に麹を育てる。できた麹は蔵の地下120mより採水した霧島山系伏流水を使って一次もろみに。そこへ二次原料として地元で採れた芋、それも掘りたての芋を加え発酵させ、蒸留する。完成した焼酎を入れる瓶も自分たちでセットし、瓶に貼るラベルも一枚一枚丁寧に手作業で貼られている。地域と密接に関わり、昔ながらの焼酎造りを代々続けてきた。



杜氏となった中村さんは、昔ながらの製法を踏襲しながらも、麹を麹室で育てる時に従来と違う衝撃的な決まり事を2つ作った。それは「機械的な熱源を使用しない」ことと「菌に寄り添う」ことである。100年以上の歴史がある中村酒造場、当たり前だが昔はエアコンや扇風機といった物は無く、それでも杜氏は麹を大切に育て焼酎を仕込んでいた。時代の移り変わりの中で、人間の基準に合わせて人間が働きやすいようにコントロールされてきた製麹の工程を、菌が持っている増殖のスピード感や活発になる時間帯に合わせて、人間が寄り添う仕込みをすると決めたのである。人間は己が持つ感性を鋭く研ぎ澄まそうと神経を集中し、五感をフル活用して自然と対峙する。今まで大切に守ってきた「手づくり」のその先に、自分たちにしかつくれないものを創ろうとしているように感じた。
蔵の人たちからは反発があったが、中村さんには歴史に裏付けされた確信のようなものがあった。とはいえ実際に菌に寄り添うことは口で言うほど楽なものではなく、昼夜関係なく麹に付きっきりで温度管理をしなくてはならない。まるで赤子の世話をするように麹室に寝泊まりする日が何日も続いた。そして苦労して完成させた麹を手にした瞬間、手触りも見た目にも明らかな違いを感じた。麹ひと粒ひと粒が綺麗で、麹葢から麹を集めるときにサラサラサラーと流れ落ちていく様子を見たときはとても嬉しかったという。「自分が感じた確信はやはり本物だった」そして、現代の中村酒造場としての麹づくりを確立した瞬間だった。

麹室に棲んでいたもの
「麹」とひとことに言ってもその中にはいくつか種類がある。鹿児島の芋焼酎は100年ほど前までは日本酒に倣い「黄麹」で仕込んでいたが、温暖多湿の鹿児島では雑菌が繁殖してなかなか品質が安定しなかった。そこで、大蔵省税務監督局技師として国から鹿児島に来ていた河内源一郎氏が、泡盛造りに使用されている「黒麹」に目をつけ研究し、1910年に河内黒麹菌の培養に成功、芋焼酎造りに使用するようになった。黒麹菌は酒の製造過程でクエン酸を大量に生成するため、雑菌による腐敗を抑えることができるという大きな特徴がある。これにより芋焼酎造りの精度が格段に向上した。そして黒麹菌を研究する中、突然変異で生まれた「白麹」も糖化能力に優れた麹のため現在では使用する蔵も多い。
「麹は畜産で言ったら餌の部分なんですね、餌をつくる素である種麹は長年買うのが当たり前になっていて実はあまり詳しくない。麹にこだわりを持って焼酎を造っているけれど、種麹にまではこだわれてないなと思うようなったんです」少し湿度の高い麹室の中で大好きな麹の話を語る中村さんのギアはどんどん上がっていき、まるでサウナの熱気の如く降りかかってきた。「畜産でも、どんな飼料を使い、どんな環境で、どんな人が育てているかなど、ブランドづくりの上でとても重要。焼酎造りでもそこを研究してチャレンジしたかった。自分でつくった種麹から麹を育ててこそ、こだわりと言えるのではないか」。中村さんの話は激しさを増し、私のメガネは白く曇り視界が奪われていった。
焼酎をつくる時にまず教わるのが、黄・白・黒の麹はそれぞれ仲が悪いから一緒に仕込んではダメだということ。黄麹は焼酎には向いていない、白麹と黒麹は一緒に仕込んでも黒麹が勝ってしまう。その教えが当たり前だった。この当たり前を疑うところから中村さんの種麹づくりが始まった。

麹室に麹菌が存在しているのかを確かめるため、熱々の蒸した米の上に、熱々のタオルをギュッと絞ってかけ、麹室の中で数日間放置する。それを天井付近、足元などいろいろな場所で試し、また時期も関係しているのかと四季を通じて試し、数年の研究ののち、最終的に麹室に漂っている麹菌が付着してできた種麹は、黄・白・黒の三つが共存しているものだった。これまでに教わった常識が一気に覆された。さらに三つを新たに蒸した米に移し培養してみると、なんと一番多かったのは黄麹だった。ここでもまた常識は覆された。「黒麹が強いと言われているのになんで黄麹が勝ったのだろう」不思議に思ってその黄麹を調べてみると〝黒麹と白麹の特性も併せ持った新たな黄麹〟であることが判明したのである。長い歴史の中で麹室で使われてきた三種の麹、また、この空間で代々焼酎をつくってきた杜氏たちの努力、苦労、泣き、笑い、感動、興奮、そして134年の歴史が詰まったハイブリッド麹をついに見つけ出した。

しかしハイブリッド麹を使って上手く発酵する確証はまだ無く「もし失敗したら」という迷いがあった。そんな心境の中、世界中で発生したパンデミック。「このまま何もしなかったら絶対に後悔してしまう、やるなら今しかない。命懸けでやろう」。チャンスは一度きり、切迫感にも似たギリギリの状態で開始した2020年の仕込み。発酵が始まるまでひと時も気が休まらない日々が続く。歴代の杜氏も背中を押してくれたのだろう、ハイブリッド麹は見事発酵し中村酒造場25年ぶりの新銘柄『Amazing』が完成したのである。
2年目となる今年もAmazingは発売された。「今年はなかなか発酵せず『もうだめだ』と諦めかけた日の夜中、見守っていた甕の中から鼻をツンと刺激する発酵臭を感じた時は心底嬉しくて涙が出ました」。
体力と精神力を削り完成させた今年のAmazingにはあの日流した嬉し涙を込めて『Tear Drop』と名付けた。

造り手であると同時に、
伝え手である必要もある
『Amazing』の素敵なエチケットは油絵画家の今井麗さんに描いてもらったもの。「好きな作家さんの作品や、素敵な芸術は見ていてうっとりとしてしまう。お酒も美味しいと気分が良くなる。どちらも人を酔わせるものだと思うんです」。と嬉しそうに話してくれた。
仕込み真っ只中にもかかわらず長時間にわたって丁寧に案内をしてくれた中村さん。「ただ良いものをつくるだけでは伝わらないことも多い、先人たちから伝わる仕込みの技術とともに、どんな想いを込めているのかを伝えることも重要。今後、機械化がさらに進んでいくことにより、手づくりできる蔵がなくなってしまうかもしれないことに危機感を抱いている。だから造り手でありながら伝え手としても存在する必要がある」。高校生の時の体験から大学でお酒について学び、日本酒蔵、流通業界と働き、そして地元に戻ってきてからは家業を継ぎ、自分が生まれ育った地域を見つめてきた経験が、今の中村さんの心情として現れている言葉だった。家族が幸せに笑っていたあの光景を心に走り続けている中村さんだが、いつしか中村さんが周りの人も笑顔にし、中村酒造場の焼酎を飲んだ人も笑顔にしているように感じた。


若き杜氏は良き造り手であるとともに、さまざまなジャンルを巻き込んで手づくりの焼酎を日本に、世界に発信していく良き伝え手としてますます活躍していくことだろう。そんなことを考えながら飲む中村酒造場の焼酎は、熱い情熱を持った中村さんの影響か、いつものお湯割りよりちょっと熱く感じた。


-
取材・文=小林史和
-
写真=中村一平
-
取材・文=小林史和
-
写真=中村一平